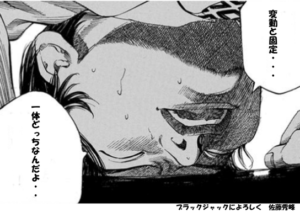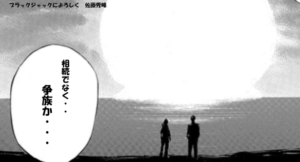こんにちは!岡山・倉敷の不動産専門FP、佐伯です。
最近、相続のご相談を受けていて、「まさかウチが…」という言葉を本当によく聞くようになりました。
ごく普通の真面目に働いてこられたご家庭が、予期せず相続税の対象になってしまう。
そんなケースが、この岡山・倉敷エリアでも、確実に増えています。
昔の常識のままでいると気づかないうちに思わぬ事態に巻き込まれてしまう。
今日は、そんな相続を取り巻く「静かな、でも大きな変化」について、
いくつかお話ししようと思います。
気づかないうちに…あなたの不動産が「課税対象」に?
「まさか」の正体として、最近最も多いのが
ご自宅など不動産の「静かな価値の上昇」です。
「地方の土地なんて、そんなに上がってないでしょ?」と思われるかもしれません。
しかし、国税庁のデータを見ると、例えばベッドタウンとして人気の総社市や
利便性の高い早島町などでも、相続税の基準となる路線価が実は5年以上連続で上昇しているんです。
ここで、具体的な例え話をしましょう。
岡山市に住むごく一般的なAさん一家です。
このご家庭の非課税ライン(基礎控除)は4800万円です。
<10年前のAさん一家>
- 自宅の土地・建物:3500万円
- 預貯金:1000万円
- 財産合計:4500万円 → 非課税で安心
<現在(2025年)>
- 預貯金:1000万円
- 自宅の土地・建物:路線価の上昇で4000万円に
- 財産合計:5000万円 → 予期せず課税対象に
Aさん一家の暮らしは何も変わっていないのに土地の評価額だけが上昇した結果、
相続税の問題が突然発生してしまったのです。
そもそも、税金がかかる「ボーダーライン」が下がっている
この「静かな地価上昇」をさらに深刻にしているのが、2015年に起きた相続税の「大改正」です。
この時、相続税がかからない非課税のライン(基礎控除)が、一気に40%も引き下げられました。
お母様と子供二人のご家庭なら、昔は8000万円まで非課税だったのが
今や4800万円まで。
つまり、そもそも課税対象になるハードル自体が、昔よりずっと低くなっている。
この低いハードルに地価が上昇した不動産が、いとも簡単に引っかかってしまうのです。
良かれと思った「生前贈与」も裏目に…
「じゃあ、贈与すればいいのか」というと、そのルールも静かに変化しています。
2024年からは、亡くなる前「7年以内」の贈与が相続財産に持ち戻されることになりました(以前は3年)。
これも具体例で見てみましょう。
倉敷市にお住まいのお母様が、二人の子供に、毎年110万円ずつコツコツ贈与を続けていたとします。
そして、贈与を始めてから6年後残念ながらお母様が亡くなりました。
- 【昔のルール】なら、亡くなる前3年分(110万×2人×3年=660万円)だけが相続財産に足し戻されます。
- 【今のルール】では、亡くなる前7年分が対象なので、このケースでは6年分の贈与すべて
つまり1320万円(110万×2人×6年)が、まるまる相続財産に足し戻されてしまうのです。
良かれと思ってコツコツ続けてきた贈与対策
逆に相続税の対象になる可能性が、昔よりずっと高くなったということです。
歴史が語る、相続税の「本当の力」
この相続税というルールの本当の恐ろしさはその影響が一代で終わらないという点にあります。
歴史を紐解けば、その強力な実例を見ることができます。
新一万円札の顔、渋沢栄一。
資本主義の父」と呼ばれた彼が築いた莫大な資産も、相続税の前では無力でした。
彼のご子孫は、今も様々な分野で活躍されていますが
その裏側で一族は相続税との長い闘いを強いられてきたのです。
資産のほとんどが、分けにくい田園調布の「土地」だったため世代交代のたびに
課される莫大な相続税を支払うため、泣く泣くその土地を切り売りし続けるしかなかったのです。
これは、相続対策の成功例ではありません。
むしろどんなに偉大な人物が築いた資産であっても一個人が相続税という
国家のルールに抗い続けるのが、いかに困難であるかを示す強烈な実例なのです。
まず、この「変化」を知ることから始まる
土地の価値が上がり税金のボーダーラインが下がり節税のルールも厳しくなる。
この「変化の流れ」を知ることが、相続対策の本当の第一歩です。
相続対策の第一歩は、資産リストを作ることや、専門家に相談することではありません。
本当の第一歩は、今日あなたがしたように
「相続税を取り巻く環境は、昔の常識が通用しないくらい厳しく変化している」という事実を、
まずはっきりと知ることです。
その認識こそが、将来、あなたとあなたの家族が後悔しないための、すべての始まりなのです。