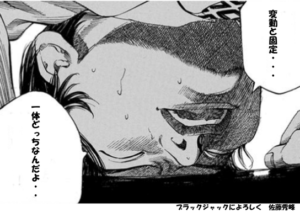女性総裁誕生、そして日本初の女性総理誕生へ。
いよいよ何か新しいことが始まる、そんな雰囲気がしてきましたね。
今回は、一旦さまざまな政治信条はさておき、「もし高市さんが総理大臣になったら」という一点に絞って
私たちの生活に最も身近な『住宅ローン』がどうなるのかをシミュレーションしていきましょう。
金融や経済の専門知識は不要です。あなたの未来の家計にどう関わるか、という視点で分かりやすく解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。
結論:金利に「綱引き」が発生!変動は低空飛行、固定はじわり上昇か
いきなり結論から申し上げると、高市新総裁の経済政策は、住宅ローン金利に「変動金利は低く抑えつけられ、固定金利は上へ引っ張られる」という、まるで綱引き(つなひき)のような、正反対の力をかける可能性を秘めています。
この「金利のねじれ現象」の謎を解くため、
2つのキーワード、「金融緩和」と「積極財政」に注目してみましょう。
【変動金利】が上がりにくい理由:キーワードは「金融緩和の継続」
変動金利タイプのローンを考えている方にとって、高市氏のスタンスは当面追い風となるかもしれません。
彼女は、「景気が本格的に上向くまで、大胆な金融緩和は続けるべきだ」と強く主張しています。
金融緩和とは日本の中央銀行である「日本銀行(日銀)」が世の中にお金の量を増やし、金利を低く誘導する政策です。
高市氏が総理である間、政府は日銀に対して「まだ利上げは早い」という圧力をかけ続けることが予想されます。
そのため、日銀も変動金利の基準となる「短期金利」の引き上げには極めて慎重になるでしょう。
もちろん、2024年に日銀は「マイナス金利政策」を解除しており、金利ゼロの時代は終わりました。
しかし、高市氏の意向は、その後の利上げペースを非常に緩やかなものに留める要因となり
私たちの変動ローン金利も、急上昇するリスクは当面抑えられる可能性が高いのです。
【固定金利】が上がりやすい理由:カギは「日銀」の動向変化
一方で、全期間金利が変わらない「固定金利」(フラット35など)は、上昇圧力がかかる可能性があります。
カギを握るのは、国債の最大の買い手である「日本銀行」のスタンスの変化です。
▼ アベノミクス時代に金利が上がらなかった理由
まず、なぜアベノミクスで政府が国債を大量に発行しても金利が上がらなかったのか。
それは、政府(売り手)が市場に供給する国債を、日本銀行(最強の買い手)がそれを上回る勢いで買い取っていたからです。市場に出回る前に日銀が吸収してしまうため、国債の価値は下がらず、金利も低いまま安定していました。
▼ 今、そしてこれから
しかし、その状況が今、大きく変わりました。日銀は2024年に異次元の金融緩和を終え、
国債の購入ペースを少しずつ減らしていく「金融正常化」へと舵を切っています。
ここで高市新総裁が積極財政のために国債の発行を増やした(=売りに出す量を増やした)場合、
最強の買い手だった日銀が購入を控える中で、売り物だけが増えることになります。
そうなると、シンプルな需要と供給のバランスが崩れ、国債の価値(価格)が下落します。
国債の価格が下がると、利回りである長期金利は上昇します。これが、固定金利が上がりやすくなるメカニズムです。
【重要】金利が0.5%違うと、返済額はどれだけ変わる?
言葉だけではイメージが湧きにくいかもしれません。
ここで、金利がわずか0.5%違うだけで、月々の返済額と総返済額にどれほどの差が生まれるか見てみましょう。
例えば、3,500万円を35年ローンで借り入れた場合を考えてみます。(元利均等返済)
もし金利が1.0%なら、毎月の返済額は約98,823円。
35年間の総返済額は約4,150万円になります。
これが金利1.5%になると毎月の返済額は約107,247円に増え、
総返済額は約4,504万円にまで膨らみます。
その差は、月々で約8,400円、そして総額ではなんと354万円にもなるのです。
月々で見ると少しの差に感じるかもしれませんが、35年間という長い期間では高級車一台分に相当する
大きな差になることがお分かりいただけるかと思います。
まとめ:未来のマイホームのために、今あなたができること
高市新総裁の政策がもたらす可能性のある「金利のねじれ」。
これを踏まえ、これから住宅ローンを組むあなたが取るべき行動は3つです。
- 自分のリスク許容度を知る 「多少金利が上がっても、月々の返済額を抑えたい」のか、「将来の金利上昇は怖いので、今のうちに返済額を確定させたい」のか。まずはご自身の性格や家計の状況を冷静に分析しましょう。
- 固定金利の「今」の金利を必ず確認する 変動金利の低さに目が行きがちですが、まずは「フラット35」など固定金利の現在の金利を必ず確認し、それを基準に検討を進めましょう。
もし固定金利が許容範囲内であれば、それは将来の安心を買う有力な選択肢となります。 - 複数の金融機関に相談し、シミュレーションを行う 一つの銀行だけでなく、複数の銀行のローン担当者に相談し、変動・固定両方のパターンで詳細な返済シミュレーションを出してもらいましょう。
専門家と話すことで、自分に合ったローンがより明確になります。
新しいリーダーの政策は、私たちの生活に直結します。
難しいニュースだと敬遠せず、正しく理解して、賢い住宅ローン選びに繋げていきましょう。
あなたのマイホームの夢が、最高の形で実現することを願っています。
ただこの予想はあくまでも予想ですので。
外れることもあること、ご理解くださいね。