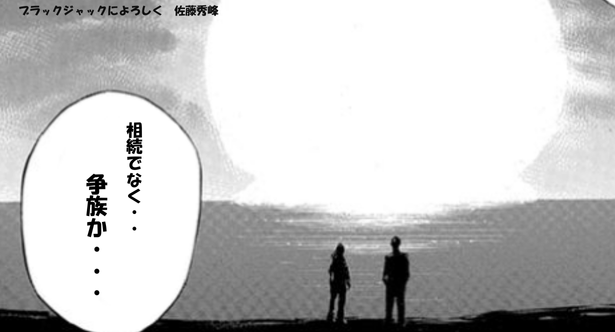「相続でもめるのなんて、お金持ちだけでしょ?」
岡山でFPとして仕事をしていると、この言葉を本当によく耳にします。
それ、きっとテレビドラマの影響ですよね。
立派な和室に親族一同がずらりと並んで、弁護士が神妙な顔で遺言書を読み上げる…。
「〇〇家の全財産は、長年尽くしてくれたお手伝いの愛子さんに譲る!」なんてセリフが飛び出して、
テーブルがひっくり返る、みたいな。
ああいう派手な「争族」は、見ていて面白いですけど、現実の世界ではまず起こりません。
むしろ、本当の相続トラブルは、もっと静かに、私たちのすぐ隣で、ごく普通の家庭で起きているんです。
データが示す、ちょっと怖い現実
これ、僕の肌感覚だけじゃないんですよ。
裁判所のデータを見ると、相続でもめている家庭の約77%が、遺産5000万円以下の家庭なんです。
一方で、相続税がかからなくなるライン(基礎控除)は、
「3000万円+600万円×法定相続人の数」で決まります。
例えば、お母様とお子様二人のご家庭なら、4800万円です。
この二つの数字、ほぼ同じです。
そうなんです。
ぶっちゃけ、「うちは相続税の心配がないから、対策は必要ない」と考えているご家庭こそが、
「一番トラブルの当事者になっている」
というのが現実なんです。
なぜなら、税金の心配がないから、「じゃあ、どうやって分ける?」という、
もっともめやすい問題への準備を全く何もしていないケースがほとんどだからです。
一番の原因は、やっぱり「実家」
じゃあ、なぜ普通の家庭がモメるのか。
岡山・倉敷エリアでも、一番の原因は不動産です。特にみんなが育った「実家」。
預金なら電卓を叩けば1円単位で分けられますけど、家はそうはいきません。
例えば、長男は「親が残してくれた家に住み続けたい」
でも妹は「私にも権利がある分は、現金でちょうだい」
さあ、どうしますか?
長男に妹へ渡すだけの現金がなければ、結局思い出の詰まった家を売るしかありません。
家も、そして家族の仲もバラバラに…
なんて、笑えない話が本当にたくさんあるんです。
それともう一つ、よくあるのが「共有名義」のワナですね。
前の相続のときに、「とりあえずみんなの共有名義で」と安易に決めてしまった不動産。
いざ次の相続が起きたときには関係者がネズミ算式に増えていてもう誰も手が付けられない…。
なんてことも、倉敷の古いお宅では珍しくありません。
やっかいなのは「お金」より「感情」
それに相続って、お金だけの話じゃないから面倒なんです。
「感情」ってやつですね。
「長女がずっと倉敷の実家で親の面倒を見てくれたじゃないか」
「いや、兄さんは岡山市内で家を建てる時、親から援助を受けていたはずだ」
親御さんからすれば、全部子供への愛情です。
でも、その想いをちゃんと「遺言書」のような形にしておかないと、
残された子供たちから見ればただの「不公平」のタネになってしまう。
良かれと思ってやったことが、後で恨みを買うなんて悲しすぎますよね。
法律では、こうした「気持ち」の部分を証明するのは、ものすごく難しいんです。
「介護の貢献(寄与分)」を主張しても、認められるのは本当に特別なケースだけ。
「昔の援助(特別受益)」だって、明確な証拠がなければ、ただの「言った、言わない」の水掛け論です。
だからこそ、親御さんが元気なうちに想いをちゃんと形にしておく必要があるんですね。
じゃあ、今日、この記事を読んだあなたが何をすべきか
結局、相続でもめるかどうかって、資産の額じゃないんです。
「分けにくい不動産があるか」「相続人が複数いるか」。
ほとんどのご家庭が、この条件に当てはまるはずです。
じゃあ、この記事を読んだあなたがまず何をすべきか。
「やっぱり専門家に相談…?」と思いますよね。も
ちろん、それも一つの手です。
でも、ちょっと待ってください。
例えばお医者さんに行くとき、「どこが、いつから、どう痛いのか」を、
何も準備せずに行きますか?
行かないですよね。
相続の相談もこれと全く同じです。
まずやってほしいのは、ご自身の「資産リスト」を作ってみること。
「全部なんて、とても…」と感じるなら、せめてご自宅など不動産だけでも結構です。
その不動産を、「誰に、どうしてほしいのか」を少し考えてみる。
権利証や固定資産税の納税通知書がどこにあるか、確認しておくだけでも立派な第一歩です。
たったそれだけでも、漠然とした不安が、具体的な「課題」に変わります。
冒頭にも書きましたが、
一番の問題は「うちには財産なんてないから、モメようがないよ」と笑いながら
この最初のステップすら踏み出さないことなんですよね。